FRG-7000、そう、「7000」なんです...今更? なーんて思われますが、FROGマニアとしては非常に気になる1台です。
ことの始まりは昨年末、セカイモンのオークションで残り5分のFRG-7000を発見。
セカイモンはしばらく使って無かったので、支払方法やら住所(!)を更新して落札完了。
(引っ越ししてから使ってなかったのがビックリ...)
で、イギリスから届いたのがコレ。そこそこ美品です。コンセントもイギリス仕様。

1.電源トランス・電圧設定の変更
イギリス仕様なので、トランス電圧設定の変更が必要です。
サービスマニュアルでは、「輸出モデルに限りマルチ電圧トランス使ってます」とあります。

配線図はコレ。

実際の配線。んーーー、240Vですわ...(あたりまえ)
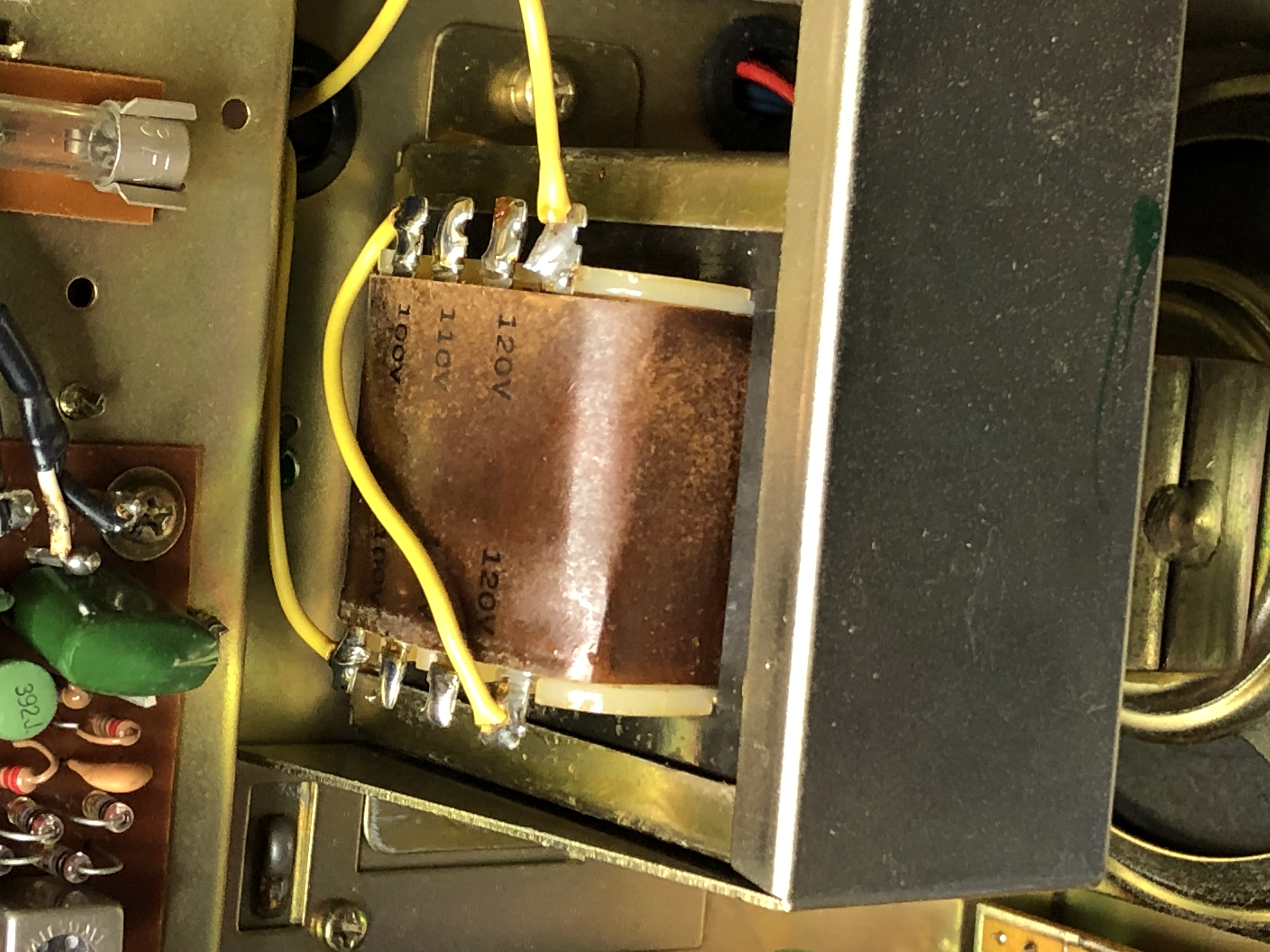
日本仕様、100Vに配線組み直しました!

ヒューズも交換しました。240V-0.5A ですが、100V-1.0A とあります。
手持ちが4.0Aしかなかったので、とりあえずコレに交換。
2.MHz表示がおかしい・VFO軸がカックンカックン...これは問題だ...
VFO軸:軸受けならなんとかなりそうですが、バリコンが逝ってるのであれば、要交換です。
(動画) MHzのセグメント表示は正常なのですが、論理演算がおかしい。+20MHzになっている...13755kHz RNZ.Pacific受信してます。
MHz表示はおかしいですが、lock/unlockは正常ですし、受信そのものも超正常。
FRG-7と同様、非常に感度が良いです。Sメータもガンガン振れてイイ感じ。
駄菓子菓子!
玉切れしているムギ球があるので、交換部品をeBayで検索したのですが...全く出品されていない!
FRG-7やFRG-7700だと大量出品あるのですが、FRG-7000用は無い!
はてさて、どーしようかと、思いを巡らせてたところ...
3.ヤフオク!でもう一台!!
「通電のみジャンク品」が出てましたので、速攻で落札。
フロントパネルや外装は酷いですが、イギリス品パーツを移植しようと思います。

エージング初日は全体的に感度が悪かったのですが、ATTスイッチ on/off を繰り返したところ、感度復活しました。
ATT用リレーの不調(接点腐食)が原因でした。多分、要交換です。
よく見るとパーツの色、輸出モデルは黒色、国内モデルは茶色なんですね。

フルレストアのおおまかな目標です。
・内部の掃除
・フロントパネル、外装の交換
・玉切れのムギ球交換(LEDにするかも...)
・ケミコン交換
・RF調整
・IF(1st~3rd)調整
・AFの改善(スピーカー交換含む)
・VFOトラッキング調整(中心周波数と周波数表示が約1kHz下方にずれている)
・ATTリレーの交換
・その他
多分...夏頃までかかりそうです...。
IC-R7000のレストアはいつになるやら笑
それではまたっ!